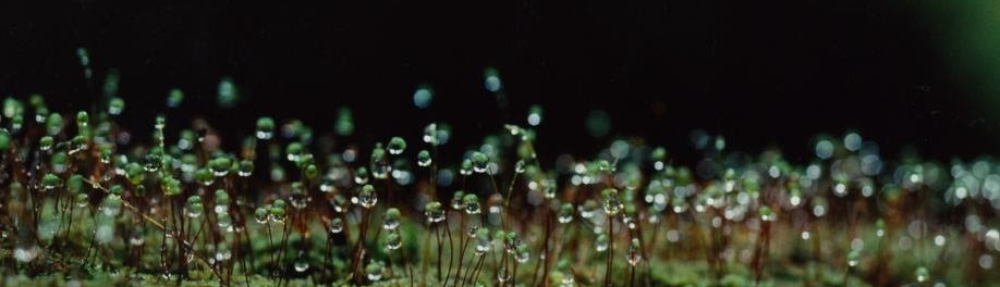對馬誠也理事長(以下、對馬):
ありがとうございます。次に、「マルチモーダルAIの進化」があります。この部分は、素人でもなんとなくイメージできますので、ここは今後必要に応じてお聞きしたいと思います。
わたしとしては、「大規模言語モデル(LLM)」について興味があるのですが、よくわかっていないものですから、この点についてお聞きしたいと思います。
その理由は、わたしが現在取り組んでいる研究に役立つのではないかと思っているからです。わたしたちは10年以上前から新しい土壌病害管理法(ヘソディム)を提案してその普及に取り組んできました。その結果、農研機構と県が中心になって膨大なデータを基にしたヘソディム支援AIアプリ(商品名:HeSo+、ヘソプラス)が開発され、その販売を当NPO法人が行っています。このAIアプリの特徴は膨大なデータを基にAIが圃場毎の診断、評価、対策を支援できることを紹介しているのですが、その次の段階として、膨大なデータがなく、生産者や指導者が圃場観察等により整理した少ない記述情報から、意思決定を支援する情報を提供することができるものはないかと考えていました。
そう考えている時に、遠藤さんからLLM(大規模言語モデル)のお話を聞いたものですから、とくに、「LLMの進化」により、上述したような『少ない記述情報』から『適切な支援をすることが可能になるのか、あるいはすでに可能になっているのか』、などについて教えていただけないでしょうか。
遠藤隆也会員(以下、遠藤):
AIの進化により、数年間の記録を整理し、翌年の診断や対策に役立てることは十分に可能になると考えられます。特にLLM(大規模言語モデル)の進化は、従来の深層学習が苦手としてきた「少ないデータからの知見抽出」や「文章の整理」において、大きな可能性を秘めています。
A. LLMの進化がもたらす変化
従来の深層学習が膨大なデータ(ビッグデータ)を必要としていたのに対し、LLMは**「事前学習」**というプロセスを経て、膨大なテキストデータから言語の構造や文脈をすでに学習しています。これにより、特定のタスクを学習させるためのデータが少なくても、精度の高い結果を出すことが可能になりました。これは、農家の皆さんが記録した数年分のデータからでも、有益な情報を引き出せることを意味します。
1. 散在した記録からの知識抽出
これまで文書で記録していた病害の発生、その際の症状、対策、そしてその結果といった記録は、LLMによって時系列や因果関係に基づいて整理されます。たとえば、「2023年5月、圃場Aでトマトの青枯病が発生。葉が萎凋し、根元が黒変したため、〇〇社の農薬を散布。その後、症状は改善傾向」といった記録が複数あった場合、LLMは「トマトの青枯病の初期症状は葉の萎凋と根元の黒変であり、〇〇社の農薬が有効である可能性が高い」といった一般的な知識を抽出できます。さらに、異なる圃場や作物の記録を横断的に分析し、共通のパターンや傾向を見つけ出すことも可能です。
2. 新たな病害への対策提案
過去のデータにない新たな病害が発生した場合でも、LLMは類似の症状や関連する病害に関する既存の知識を基に、対策を提案できます。例えば、過去の記録にはない「新しいカビ病」が発生したとしても、LLMは「過去に発生した他のカビ病の対策」や「その症状に有効だったと記録されている資材」を参考に、考えられる対策案を生成することができます。これは、生産者や指導者の「経験と勘」をデジタル化し、より多くの知見を組み合わせることで、人間の思考プロセスを支援するような役割を担います。
具体的な応用例として、
■圃場ごとの傾向分析:過去の記録から、特定の圃場や特定の作付けパターンで発生しやすい病害の傾向を自動で分析し、その情報を基に予防策を提案します。
■対策効果の可視化:「この病害にはこの農薬が効果的だった」という記録を抽出し、対策前後の状態を比較して効果を数値やグラフで可視化します。これにより、効果的な対策を体系的に判断できるようになります。
■作業日誌の自動生成:生産者が入力した断片的な記録を基に、より整理された形式の作業日誌を自動で生成。過去の活動を振り返る手間を大幅に削減します。
などが考えられます。
對馬:
LLMについて具体的な例を挙げて説明していただきありがとうございます。とてもよく理解できました。少し前まで、「膨大なデータを集めて課題解決」、「将棋・囲碁でAIが人間に勝利」などが言われた際に「深層学習を活用したAI」が有名になったのですが、これからは、「データが少ない記述情報」を基に意思決定を支援するる「LLMを活用したAI」も出てくるということですね。
ただし、HeSo+の活用でも課題はあるのですが、LLMの場合、『少ない記述情報』を基にして意思決定を支援する際には、AIアプリ(HeSo+)以上に、『出力された結果』が現場で使えると考えてよいかどうかについて、『適切に判断できる人材』や『判断を支援する仕組み』も作る必要があるように思いました。
LLMを農業現場で使えるようにこれから勉強していきたいと思いますのでよろしくお願いします。
遠藤:
なお、少し先の説明になるかもしれませんが、マルチエージェントを活用すると、上述の説明全体を、下記に示すようなWebページとして、表現することも可能です。
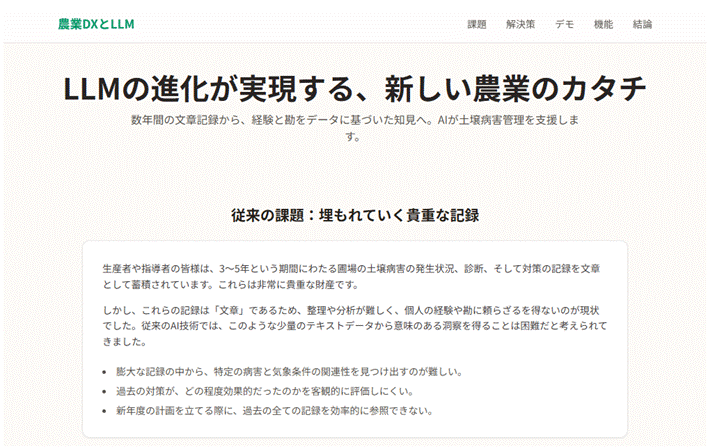
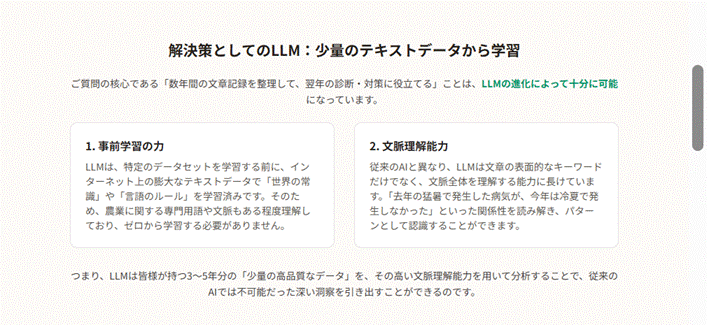
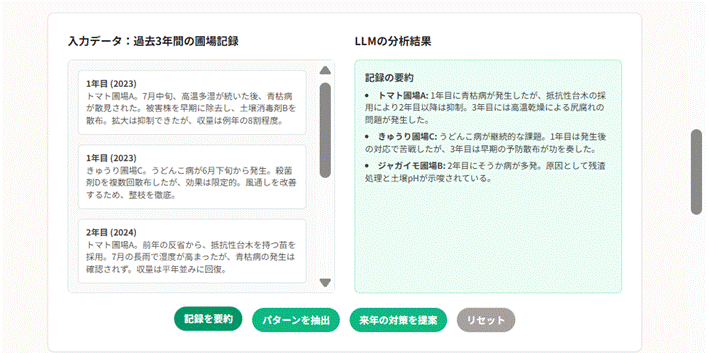
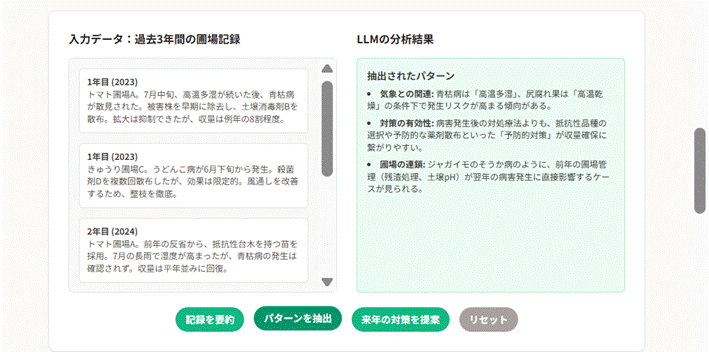
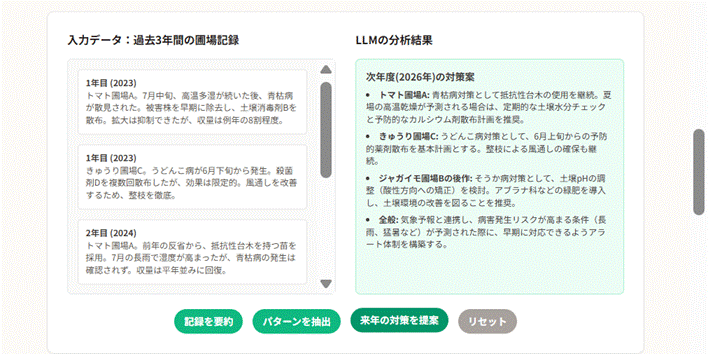

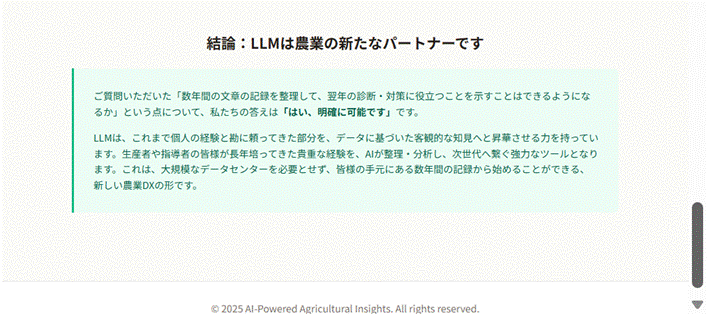
對馬:
LLMについての具体的な例を挙げて説明していただきありがとうございます。とてもよく理解できました。少し前まで、「膨大なデータを集めて課題解決」、「将棋・囲碁でAIが人間に勝利」などが言われた際に「深層学習を活用したAI」という単語が有名になったのですが、これからは、「データが少ない記述情報」を基に意思決定を支援するる「LLMを活用したAI」も出てくるということですね。
ただし、HeSo+の活用でも課題はあるのですが、LLMの場合、『少ない記述情報』を基にして意思決定を支援する際には、AIアプリ(HeSo+)以上に、『出力された結果』が現場で使えると考えてよいかどうかについて、『適切に判断できる人材』や『判断を支援する仕組み』も作る必要があるように思いました。 LLMを農業現場で使えるようにこれから勉強していきたいと思いますのでよろしくお願いします。
對馬:
次回は「マルチエージェント」について、教えていただきたいと思います。