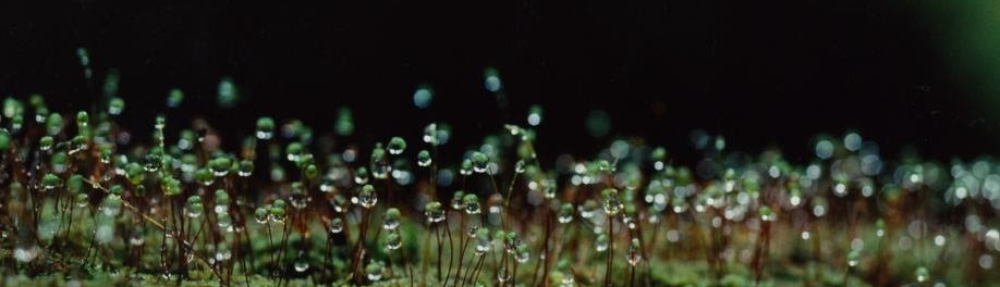對馬誠也理事長(以下、對馬):
つぎに、少し話題を変えて、内発的Wantと外発的Shouldについてお話いただきたいと思います。遠藤さんは、この内発的Wantと外発的Shouldを融合することを考えられたとのことですが、どのようなことをしている時に、両者の融合ができる(あるいは必要だ)と考えたのでしょうか。
遠藤隆也会員(以下、遠藤):
前にもお話ししましたが、デジタル通信サービスを提供しているときに、サービス仕様を自分でデザインし、そのデジタルサービスが実際に使われ始めると、ユーザーインタフェースやユーザーエクスペリエンスが基本的な課題として持ち上がってきていました。そこで、ヒューマンインタフェースの研究を「すべきである」と考え始めたのです。これが外発的shouldです。
もともと、若いころから、人間自身、哲学、宗教、脳科学、意識の流れ(Stream of Consciousness)、ヒューマンコミュニケーションなどの勉強をしていました。これが「内発的Want」です。これをを何かの機会に、自分の業務としての研究としていくことはできないかと模索しておりました。
丁度その時に、タイミングよく、電電公社が民営化(NTT)され、組織全体で大きなトランスフォーメーションを推進することになり、(私自身がその変革の推進役の一員に選ばれて)新しい研究所を立ち上げることになりました(これも外発的Should)。ここで、自分自身の内発的Want(やりたいこと)と企業からの外発的Should(やるべきこと)を結びつける機関として、「ヒューマンインタフェース研究所」の創設に携わることになりました。
對馬:
内発的Wantと外発的Shouldをつなぐ機関として研究所の創設に携わったわけですが、当時としてはとても珍しい研究所だったのではないかと思います。現在でいうならば、研究所自体がイノベーションだったのではないかと思います。しかし、現在でもイノベーションを日本で行うのは容易ではありません。当時も、周囲に理解されないこととか、反対されたことなどいろいろあったのではないかと思います。その点について教えてください。
遠藤:
その当時、この研究所は、日本の企業では全く珍しい名前の研究所でした。それまでの研究所の名前というと漢字の名前の研究所が普通でしたが、NTTの中でも初めてのカタカナの名前の研究所である「ヒューマンインターフェース研究所」ということで、センセーショナルな出来事でした。このころ、NTTの通信研究所全体では約3000名の研究者がおりましたが、その内の約300名が、言語メディア研究、画像メディア研究、知能ロボット研究の各々の分野で研究する「ヒューマンインターフェース研究所」に所属することになりました。
對馬:
それでは、内発的Wantと外発的Shouldをつなぐために、どのような研究あるいは技術開発をこの「ヒューマンインターフェース研究所」で行ったのでしょうか。
遠藤:
私は、この言語メディア研究、画像メディア研究、知能ロボット研究の各々の分野で研究する約300名からなる研究所全体の研究企画部長として、所長の下で、研究所を経営する業務(研究5か年計画、研究企画、予算要求・予算配分、人事任用、給与・ボーナス、総務など)を遂行していました。これは、私にとっては、外発的Shouldでした。これだけをやっていたのでは、自分の内発的Wantを実践することは出来ません。
内発的Wantと外発的Shouldをつなぐために、言語メディア研究分野の中に、「言語メディア方式研究グループ」を新設しました。そして、その中で自分の根本的な疑問にチャレンジするために、コンピュータ・ヒューマンインタラクション(Computer-Human Interaction :CHI)、認知科学、行動科学(その後に行動経済学)、自然言語処理、機械翻訳、ニューラルネットワークそして人工知能の研究を進め、研究企画部長の職を遂行しながら、学会活動、海外出張や海外著名者の招聘・滞在研究員化を実践したのです。
對馬:
コンピュータ・ヒューマンインタラクションと言っても実に多くのすべきことがあるのですね。その上、認知科学、行動科学、自然言語処理・・・の課題があるわけですから、遠藤さんが考える世界の広さを感じます。それでは、少し具体的にいろいろお聞きしたいと思います。新しい研究所の創設で、とくに時間をかけて取り組んだことなどあったら教えていただけないでしょうか。
遠藤:
その当時は、「Japan as No.1」にしなければということで、外界は、国も会社も何か新しい事をやらなければという雰囲気でした。ただ、内界すなわち研究組織・研究員の間では、新しく取り組むべき具体的な研究内容については、喧々諤々でした。そこで、自分たちの新たなテーマに取り組むために、米国でのコンピュータ・ヒューマンインタラクションの学会、マサチューセッツ工科大学、当時の初期のシリコンバレーの方々との議論・交流に時間をかけて取り組みました。
對馬:
「Japan as No.1」(Ezra Feivel Vogel:1979)はわたしも大学時代に読みました。学生としては、日本が世界をリードしているのだなと感じたことを思い出します。企業の方は、当時、まさに、そのことを強く意識していたわけですね。
個人的には、今の日本の企業の方はそうした意識がかなり低下していて、そうした意識の低下が日本でイノベーションが出てこないことと関連しているように思うのですが、遠藤さんはどのようにお考えでしょうか。わたしたちのNPO法人はイノベーションを目指す人材育成も考えて立ち上げた経緯もあるので、是非、お聞きしたいと思います。
遠藤:
実を申しますと、私は、今の日本の企業を離れて、クラウド上での「スローなユビキタスライフ」を始めて20年になります。この20年間、今の日本の企業の実態を実体験しておらず、正確なお答えにはならないと思いますが、間接的にお聞きしている情報から、私なりの考えを述べさせて頂きます。
では、意識の低下といわれているところをどうするか、という点について考えていきたいと思います。
私は、第二次世界大戦の最中に生まれた人間です。戦後は、皆が「どう生きていこうか」で精一杯でした。学校に入っても、先生方は、(手のひらを返すがごとく)「これまでの日本の教育は間違っていた、意識を変えていかなければならない」。そんな時代を生きて、がむしゃらに皆が頑張って、やっと「Japan as No.1」に辿りついたと思った時にバブルがはじけ、また、根本的に「意識を変えていかなければならない」と言われる時代になってきた訳です。
前にも述べましたが、私は若いころから、人間自身、哲学、宗教、脳科学、意識の流れ、ヒューマンコミュニケーションなどの勉強をしていました。この中でも、とくに「意識」については、「勉強をして勉強をして、自分にとって分かった気になっても、すぐに遠ざかっていく概念」でした。
40年前頃に、この意識に関する研究が、(これは、数千年前から哲学や宗教の世界では行われていたことですが)普通の私たちにも見えるようになってきました。今回のブログのご質問のお陰で、私も、この世界に没頭していた日々を思い出しました。「意識を変えていかなければならない」。そのためには、まず「意識とはなにか」について、「外界」から学び、そして、「内界」としての自分の中で実体感していくことが、今、求められていることと思います。
對馬:
遠藤さんの回答がとても難しくてすぐには理解できないのですが、「意識を変える」ことが簡単ではないということは理解できたように思います。これから遠藤さんと一緒に「意識とはなにか」についても勉強したいと思いますので、よろしくお願いします。